「50代」ということでプレゼントの毛色を変えてみた
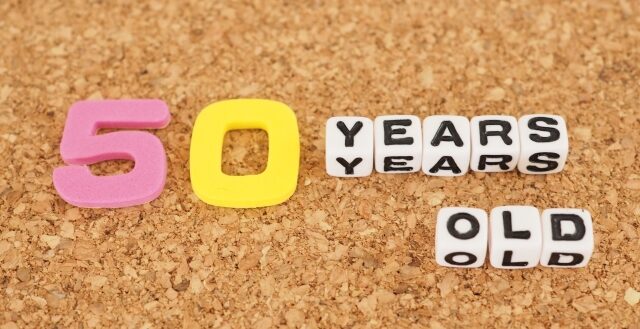
さてさて、2月にこんな記事を出したのですが、

3月に母の誕生日があったことで、
改めて「本当の親孝行ってなんだろう?」と考えました。
「今まで育ててくれたことの感謝を伝える」
「9年間お弁当を作り続けてくれた感謝を伝える」
「今でもときおり手作りのきんぴらごぼうとピーマンの肉詰めを送ってくれる感謝を伝える」
とまぁ、こんな感じで〝感謝を伝える系〟のメッセージと、それに伴うプレゼントはポンポン思いつくのですが……。
まぁ飽きたよね。
だいたい毎年、「スイーツとちょっとしたメッセージカード」みたいなプレゼントになるのですが、まぁ飽きたよね。
母「ありがとー! 届いたよ~!」
僕「よかった! 食べてみて!」
母「今年も健康に気をつけるね」
僕「健康第一だね。ただ、届いたスイーツは食べてね~」
このテンプレ会話、飽きました。
ということで、今年はちょっと毛色を変えたプレゼントをあげてみました。
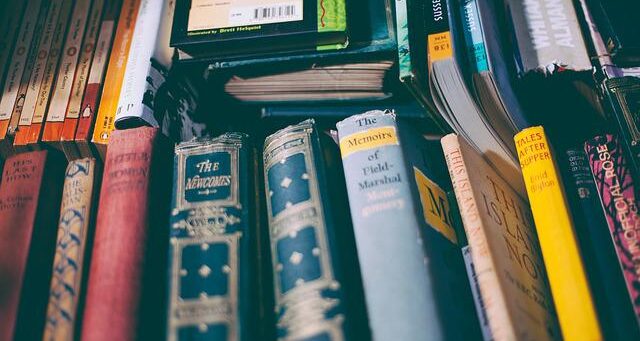
それは「本」
絵本でもなく、漫画でもなく、もちろん料理のレシピ集でもありません。
活字の本。「ザ・本」って感じの本です。
もちろん、これは僕なりの考えがあってのチョイスですので、その考えを本記事に書いていきますね。
母にあげた誕生日プレゼント
結論から言うと、母にあげたのは以下の書籍です。
【著者】本田 健
【タイトル】50代にしておきたい17のこと
【出版社】大和書房
【出版日】2012.01.10
本田氏の『50代にしておきたい17のこと』
この「しておきたい17のことシリーズ」は他にも、
『10代版』『20代版』『『30代版』『40代版』『60代版』
『20代恋愛版』『就職する前版』『理想のパートナー版』
とたくさんあり、
僕は社会人なりたての頃に『20代にしておきたい17のこと』を読んで、非常に深く多くの学びを得ることができました。
今でも、その学びが心の根底にある気がします。
なぜ、プレゼントに「本」を選んだのか?
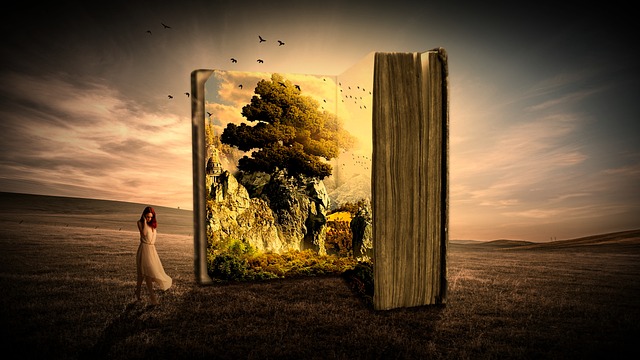
「初老の目に小さい文字はきついぜ」と、本が届いた早々母と父から連絡が来ましたが、まぁこれは想定内。
それを加味したうえで「なぜ僕が〝本〟をプレゼントに選んだのか?」
それは、〝気づき〟を得てほしかったからです。
50代を「子どもも巣立ち、自分たちの役目を終え、あとは自分たちが楽しく生きる」という〝前半戦のエピローグ〟として過ごすのではなく、
「よっしゃ! 子どもたちも出てったことだし、新しいことをどんどんやっていこうか!」という〝後半戦のロケットスタート〟として精力的に生きる。
そんな気づきを、得てほしかったからです。
もちろん、本を送ったところで、それを読むか・読まないかは、母の自由です。
しつこく「読んだ? 読んだ?」と聞くのもうっとうしいですし、僕が音読するのもちょっとめんどくさい。

『馬を水辺に連れていくことはできても、水を飲ませることはできない』
イギリスのことわざです。
どれだけ馬が喉をからしていても、
どれだけ水辺のすぐ近くに飼い主が連れて行っても、
どれだけその川に流れている水がミネラル豊富な天然水だったとしても。
「飲むか・飲まないか」を選択るのは馬自身。
つまるところ「行動するかどうかは、その人自身」ということを表しています。
このたとえでいうと「俺たちは馬か?」と、父親から重箱の隅をつつくような苦情が飛んできそうですが、まぁそれは置いといて……。
余計なお世話であることは重々承知ですが、それでも「〝気づき〟を得てほしかったから本をプレゼントした」ということを、冒頭の答えとしておきますね。
なぜ「本のプレゼント」が、 「親の気持ちに寄り添う」につながるのか?

最後に本記事のタイトルにある「親の気持ちに寄り添う」という文言について、僕なりの考えを綴っていきます。
まず「寄り添う」という言葉を聞くと、おおよそ
- 一緒にいること
- 相手の気持ちを理解しようとすること
- 受け入れること
- 安心感を与えること
が思いつくと思います。
相手の気持ちファースト。
相手が心地よさを感じてくれることをしてあげる。
だから今回の場合で言うと、母には毎度おなじみスイーツや美顔器、洋服などを上げたほうが確実に喜んでくれたと思います。

でも、僕は「寄り添う対象」を「未来の母」にしました。
その理由は、1年くらい前に、母が運転中にこぼしたある一言を思い出したからです。
「若いっていいねぇ、好きなことに本気になれて。私たち(母と父)はもう年だし、いろいろあるから好きなことばかりやってられないよ」
僕はこの言葉を聞いて無性に悲しくなりました。
なぜなら、僕はこの3年間、(主にビジネスの場面で)知り合った人たちを見て、「何歳からでもなにかを始められる」というのを目の当たりにしてきたからです。
50代でも、60代でも、70代でも。いついかなる状況に置いても人は変わることができると、知っていたからです。
「じゃあなぜ、母は〝変われない〟と思っているのか?」
「なぜ、〝変わらないこと〟を選択しているのか?」
おそらくそれは、「世間体」が原因だと思います。

僕の地元はけっこう田舎。けっっっっっこう田舎。
最寄りの駅までは「車で」30分かかりますし、
最も近いコンビニも、歩いたら40分かかります。
玄関出て5秒で海ですし、
夏の夜は、蝉の声がミセスのLIVE会場並みに鳴っています。
あ、一応言っておきますが、僕は田舎が(もちろん地元も)めちゃ好きです。
東京に2年間住んでたのですが、やっぱり自然が好きで北九州市門司区という、いい感じの田舎に引っ越しましたからね。

ただ、田舎というのは「村社会」が強い傾向があります。
やっぱり近所同士の仲、地域の結束力が強い分、どうしても「俺たち仲間だぜ」感は出てしまいますからね。
「あなたはこういう人です」というのが知らず知らずのうちに、自分にも近所の人にも刷り込まれているんだと思います。
あなたは「農家」
あなたは「片山家の長男」
あなたは「波風立てない優しい子」
あなたは「家族想いの良い子」
あなたは「将来、家に入る」
気づかぬうちに、「自分はこういう人間なんだ」と思うようになっていく。
地元は心地よいし、近所の人たちも温かい。
久しぶりにあった幼馴染はいつもフランクに話しかけてくれるし、コンビニで合う同級生も気のいい人ばかり。
嫌いになる理由がないし、むしろ大好きです。
でももし、知らず知らずのうちにその「輪」が、自分の行動を制限する「鎖」となっているのなら。
それを「断ち切れ」とまでは言いませんが、「気づく」ことが母にとってなにかプラスに働くと思い、此度の本を渡しました。
ま、余計なお世話以外の何物でもないんですけどね(笑)
僕みたいにごちゃごちゃ考えずとも、「プレゼントで本をもらう」というのは意外といいものだと思うので、もしよければ試してみてください。
【著者】本田 健
【タイトル】50代にしておきたい17のこと
【出版社】大和書房
【出版日】2012.01.10



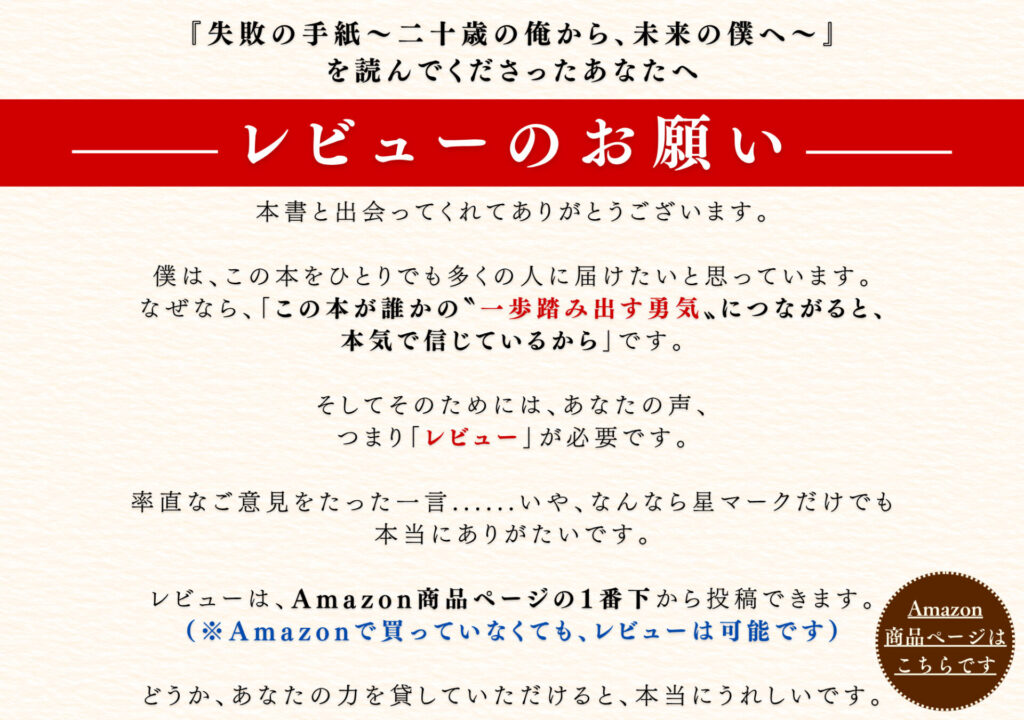



コメント