
\この記事でわかること/
- なぜ、社会人「こそ」読書が必要なのか?
- 忖度抜き!社会人必読の10冊をご紹介
- それぞれの本に関する僕のエピソード
なぜ、社会人に読書が必要なのか?
-僕が本を読む理由-
僕が読書をする理由。
それは「頭良いアピールをするため」、これに尽きます。
……すみません、冗談です。
本当の目的は「気づきを得るため」です。
少し話を変えますが、あなたは今の現状に満足していますか?
「うん! 今の人生に100%大満足! これ以上はないよ!」という人も。
あるいは、「う~ん。もう少し華やかで自由な人生がよかったなぁ……」と思う人も、それぞれいるでしょう。
これはあくまで僕の一意見ですが、「今の人生に大満足!」という人は、なかなかいないのかなぁと思います。
何を隠そう、今偉そうに文章を書いている僕自身が「100%満足してる」と、胸を張って言えないからです。
「もっとたくさんの本を世に出したい」
「もっと面白いエンタメを創りたい」
「もっと人様のお役に立てる範囲を広げたい」
抽象度が高めな目標もありますが、「もっと」という気持ちは心にあります。
もちろん、一年前、二年前、三年前と比べると、自分の人生に満足・納得できる部分は格段に増えていますが、それでも正直に打ち明けると100%満足はしていないですね。
そんな今の僕の現状。
その「現状」を創り上げているのは何かー?
それは「習慣」だと、僕は思います。
今の僕は、今の僕の習慣によって形成されています。
あるいは、今まで続けてきた習慣によって、今の僕が形成されています。
そしてその習慣を創る最も大きな材料になるのが、「価値観」です。
人はみな、自分の価値観に沿って生きています。
「港区の高級マンションに住むために稼ぐのか?
それとも、地方の安いアパート暮らしにして、仕事は最低限で趣味を楽しむのか?」
「目の前にあるショートケーキに半額シールが貼られたから、”安い”と思って買うのか?
それとも、半額シールが貼られたから、”味が落ちている”と思って買わないのか?」
「新しいことへのチャレンジは”リスクがいっぱいだ”と思って、二の足を踏むのか?
それとも、新しいことへのチャレンジは”未知のワクワクで溢れている”と思って、一歩を踏み出すのか?」
これらの選択は、どちらが良い・悪いという話ではなく、価値観の違いです。
価値観の違いが、選択の違いを生み出しているわけです。
そして、その「選択」が今の現状を創っています。
なにせ「人間は、1日に約35000回の選択をする」と言われていますからね。
価値観がまったく異なるAさんとBさんが35000回選択する日を何年も続けたら、そりゃあ「現状」も180度近く変わってきますよ。
さて、長々とウンチクを垂れてしまいましたが、
「今の現状は、あなたの価値観に基づく『選択』が生み出した習慣である」
ということは、なんとなくご理解いただけたでしょうか。
「じゃあその価値観はどうやって変わるってんだい?」という話になってきますが、これはいろいろあると思います。
「今まで体験したことのない、自分の認知の外にある体験をすること」
「自分が理想としているライフスタイルを送っている人に会ってみること」
「住む場所を変えてみること」
そして「本を読むこと」
書店に並んでいる1つ1つの本には、その著者が人生を懸けて学んだ教訓や刺激的な体験談が詰まっています。
自分の価値観では考えられないような、大胆な挑戦ストーリーに出会うかもしれません。
あるいは、読んでいるだけで涙がポロポロと出てくる、感動的なストーリーに出会うかもしれません。
それがかけがえのない『気づき』となり、コツコツ積み上げっていくことで『価値観』も徐々に変わっていくんだと思います。
-visual-selection-6.png)
僕は「一冊の本で、1つでも気づきが得られれば御の字」と思って、本を読んでいます。
これは決して一冊の本を小さく見積もっているわけではなく、シンプルに「価値観を変えるぞ!」みたいに意気込むと疲れるからです(笑)
そういうスタンスで本を読んでいる僕でも、とりわけ「この本と出会えて本当に良かった!」と思った書籍を本記事でご紹介します。
大学4年生の頃、地元の図書館で毎日朝から夕方まで本を読みまくっていたら、
「ちょっと写真を撮らせてもらってもいいかしら?」と、地元図書館誌に掲載されたほど読書好きな片山が、自身のエピソードも含めて完全独断偏見好み100%でご紹介していきます!(笑)
本記事でご紹介するおすすめ本10冊
ノリノリで書いてたらトンデモナイ文字数になっていたので、「あんたのエピソードはいいから、ひとまず本の紹介だけ見せておくれ」という方もいると思うので、以下に今回ご紹介する一覧を載せておきますね!
#1 上京物語
#2 チーズはどこへ消えた?
#3 夢をかなえるゾウ(シリーズ)
#4 死ぬ瞬間の5つの後悔
#5 こころを折らないで-父の娘の会話-
#6 エッセンシャル思考
#7 藤原和博の必ず食える1%になる方法
#8 なまえのないねこ
#9 自分の中に毒を持て
#10 嫌われる勇気・幸せになる勇気
本記事でご紹介する書籍の中には、読み放題サービス『Kindle Unlimited(キンドル・アンリミテッド)』に加入されてる場合、無料で読める本もございます。
\運営者のエピソード付き/
20代社会人が絶対に読むべきおすすめ本10冊
#1 上京物語
「え? 俺の心、覗かれてる……??」
そう思えるほど、『生き方』に迷える僕の心を鷲掴みにしたのが本書『上京物語』
僕が最もインパクトを受けた本であり、人生のターニングポイントとなった一冊です。
***
2024年4月。
24歳の僕がまだ東京で働いていた頃。
父の手術を機に、3週間だけ愛知の実家に帰省。
(その時の話はこちらの記事から)
この間いろいろ思い改めるところがあり、今まで行き当たりばったりで生きてきた人生を客観的に見つめ直していました。
幸い、父の手術は無事成功。
3週間の実家生活(有休生活)を終え、再び会社がある東京に戻ります。
その時、豊橋~東京間の新幹線ひかり号で読んだのが本書です。
新幹線の時間は約90分。
いつもは「まだかなぁ」と思い景色を眺めているのですが、この時は違いました。
もうね……。
ドンピシャすぎたんですよ。
本のストーリーと僕の状況が同じすぎ。
ちょうど本書のシチュエーションも「上京するために新幹線に乗っている青年(大学卒業前)」だったんですよ。
こんな偶然、あります?
怖いくらいの偶然ですよね?
そんなフィクションみたいな偶然も相まって、僕はもう食い入るように読みました。
さらに内容も内容。
当時の僕の生き方ー夢を全力で追うわけでもなく、かといって現実を堅実に生きるわけでもない、中途半端な生き方ーに力強い喝を入れてくれました。
5ページ、10ページ、20ページと読む最中。
「もはや、この本は俺のために書かれたんじゃないか?」と勘違いしてしまうほど、当時の僕と瓜二つの主人公がそこいたのです。
***
本書は、父が自身の息子「祐輔(ゆうすけ)」に送る手紙が物語の主となっています。
常識に流されないために。
本物の成功者になるために。
夢を夢で終わらせないために。
父が自分の人生で知り得た「生き方」を息子に届けます。
多くの人が当たり前のように思っている「常識の殻」
本物の成功者に必須の「自分の価値観」を持つ方法
今、「生き方」に行き詰まりを感じているあなたにとって、現状を打破するキッカケになると思います。
***
僕は本書がキッカケで喜多川氏のファンになり、そして「人々に勇気を届ける作家」になる夢を志しました。
本書『上京物語』は、間違いなく僕の人生における1つのターニングポイント。
常識に流され、自分を見失っているあなたの助けになってくれるはずです。
【著者】喜多川 泰
【タイトル】上京物語 僕の人生を変えた、父の五つの教え【出版社】ディスカヴァー・トゥエンティワン
【出版日】2009.02.20
-visual-selection-2.png)
本書は、読み放題サービス『Kindle Unlimited(キンドル・アンリミテッド)』に加入されてる場合、無料で読めます。(2025.03.17時点)
#2 チーズはどこへ消えた?
「やっべ……。このままじゃ一生チーズ食えんわ」
いつの間にか「安定」に走ってしまっていた僕に、「危機感」に近い気づきを与えてくれた一冊。
約80ページと1時間ほどで読了できる物語の中に、「変化」が激しい今の時代を生き抜く心構えが詰まっています。
***
二匹のねずみと二人の小人が、迷路の中でチーズを探す物語。
本書の指す「チーズ」とは、現実世界で置き換えると「自分が追い求めるもの」
もう少し具体的にするとこんな感じ。
- 夢(社長になる、プロ野球選手になる など)
- 実現したい生活(悠々自適な生活、海外暮らし、FIRE生活 など)
- お金
明確な「追い求めるもの」がある場合はそれを。
個人的なおすすめとしてはチーズを「お金」に置き換えると、すごく心に響くと思います。
当たり前のにあると思っていた「チーズ」が、ある日突然消えた……。
食料がなくなったねずみと小人。
二匹のねずみはすぐにチーズ探しへ。
探しにいってもチーズがあるかわからないし、危険なことが起こるかもしれません。
一方、二人の小人はチーズがいつか戻ってくると信じて元居た場所に。
慣れ親しんだ安全な場所。苦労することもありません。
今のあなたなら、どちらを選びますか?
***
人生に漠然とした不安を抱えている。
そしてジリジリと少しずつ、人生が悪い方向へ進んでいる気がする。
「上手く言葉にできないけど、常に自分の心に潜む影の正体を知りたい人」におすすめの一冊です。
【著者】スペンサー・ジョンソン(著)、門田 美鈴(翻訳)
【タイトル】チーズはどこでへ消えた?【出版社】扶桑社
【出版日】2000.11.30
また、本書の著者スペンサー・ジョンソン氏の関連書籍も、非常に深い学びが得られるので参考までに掲載しておきます。
「迷路の外には何がある?」
(「チーズはどこに消えた?」のシリーズ作)
「マンガでわかる チーズはどこへ消えた?」
(「チーズはどこに消えた?」のマンガ版)
-visual-selection-3.png)
#3 夢をかなえるゾウ(シリーズ)
「第一志望の最終面接。
エントリーシートそっちのけで読んでました」
僕が大学生4年生の頃に、ハマりにハマったシリーズ。
たしかちょうど就活シーズンだったと思います。
緊迫した面接前。
他大学の就活生が待機室でエントリーシートや対策ノートを読んでいる中、ずっと本作を読んでました(笑)
***
本作品は、全5シリーズ(1巻,2巻,3巻,4巻,0巻)
面白くてタメになる自己啓発小説です。
夢をかなえるゾウの神様『ガネーシャ』が、成功に導くアドバイスを「超具体的に」教えてくれます。
「今までいろんなビジネス書や自己啓発書を読んできたけど、結局何も変わらなかった……」
そう感じている人にこそ読んでほしい作品です!
抽象的ではなく具体的に教えてくれるガネーシャの教えを聞くと、きっとあなたも行動に移せるはず。
著者の水野氏が広げるエンタメ自己啓発小説。
タメになるだけでなく、面白おかしく、笑いが溢れるのも本書の魅力の1つです。
***
ちなみに、本作にハマっていた当時。
僕はインテリぶって、たくさんのビジネス書を読みふけっていたんですよ(笑)
わざわざ朝イチでカフェに行き、伊達眼鏡をかけてコーヒー片手に読書。
「俺ってできるやつじゃん♬」と、気持ち悪い優越感に浸っていました……。
しかし、どれだけ本を読んでも、一向に何かが変わる気配もない。
「成功」に近づく兆しも、「お金持ち」になる未来も見えない。
「おっかしいなぁ。本を読めば成功者になれるって、いろんな本に書いてあったのに……」
そんな僕ー重大な勘違いをしていた僕ーに、大切な気づきを与えてくれたのが本シリーズです。
その「重大な勘違い」を放っておくと2000%成功できないので、あなたも本作の中でぜひ見つけてくださいね。
【著者】水野 敬也
【タイトル】夢をかなえるゾウ1【出版社】文響社
【出版日】2021.04.08
-visual-selection-4.png)
ちなみに、夢をかなえるゾウシリーズは全部で5作あります。
どれも面白くてタメになる内容ですので、ぜひ読んでみてくださいね♬
本書は、読み放題サービス『Kindle Unlimited(キンドル・アンリミテッド)』に加入されてる場合、無料で読めます。(2025.03.17時点)
#4 死ぬ瞬間の5つの後悔
「このままだと、俺は100京%……いや、100那由他%後悔する」
本書との出会いでそう確信しました。
これまで数多くの本を読んできましたが、本書ほど「自分との対話」に没頭できる本はありませんでした。
***
本書の著者ブロニー・ウェア氏は、数多くの患者の最後を看取った介護人。
この世の生を残りわずかと悟った患者は、ブロニー氏に「死ぬ瞬間の後悔」を伝えたと言います。
フィクションではない。
後悔の涙が混じったノンフィクション。
あなたは彼らの言葉を聞いてー彼らの言葉を「本」としてこの世に残したブロニー氏の言葉を聞いてー何を思いますか?
***
全人類に唯一平等に与えられている定め。
それは「いつか必ず死ぬ」ことです。
歴史的に名を遺す偉人も、
一世一代の大企業を創り上げた稀代の経営者も、
前人未到の記録を叩き出す千年に一人の逸材アスリートも。
いつか必ず死にます。
この点に関して異論はないでしょう。
でも多くの人が「死」を「自分とは無関係のナニカ」として捉えている。
20代の人は30代が。
30代の人は40代が。
40代の人は自分に孫ができるなんて思いもしない。
本音のところ、こう思ってる方が多いのではないでしょうか。
何を隠そう、こんな偉そうに語っている僕も、つい最近までそう思ってましたから。
「死」は、いつか必ずやってくる。
でも、怖がることはない。
いつか必ず来るものだと思えば、今から後悔が少なくなるように生きられる。
そのキッカケとして、本書『死ぬ瞬間の5つの後悔』を読んでみてがいかがでしょうか。
読みながら自分を見つめなおし、未来について考え、「今」やるべきことに励む勇気をもらえる一冊です。
【著者】ブロニー・ウェア(著)、仁木 めぐみ(翻訳)
【タイトル】死ぬ瞬間の5つの後悔【出版社】新潮社
【出版日】2012.12.18
-visual-selection-5.png)
#5 こころを折らないでー父の娘の会話ー
あなたは〝引き算〟ばかりをしていませんか?
医師とイラストレーターのタッグで送る、心温まる絵本。
〝生きる〟ことの本質を突き、人生の幸せに改めて考えさせられる一冊です。
わずか44ページの間に、ハッと気づかされる言葉がいくつもあります。
絵本ゆえに話すぎるとネタバレになるので、僕があなたに問いたいのはただ一つ。
「あなたは〝引き算〟ばかりしていませんか?」
「あの人はお金があって何でも好きなもの買えるのに、私は毎月手取り20万……」
「あの子は結婚して子どももたくさんいるのに、わたしはずっと独身……」
「アイツは夢も叶えて楽しく人生を謳歌しているのに、俺はいつまでこんな仕事を……」
感じる必要もない「差」を感じて、不幸になっていないのでしょうか?
自分の人生に足りないものばかりを数えて、ついつい〝引き算〟をしてはいないでしょうか?
SNSで誰でも「比較」ができるようになった現代。
「誰とも比べずに生きろ!」というのは現実的ではありません。
だがしかし、〝今あるもの〟をしっかりと確認することは、いくら時代が変化しようと可能です。
あなたに今あるものはなにか?
そのあるものに感謝を抱けているか?
あなたは〝今のあなた〟を大切にできているか?
僕は本書を読んで涙が出ました。
引き算ばかりしてこころが折れそうになっている方は、ぜひ一度読んでみてください。
きっと心が軽くなると思います。
【著者】小住 和徳(文)、上岡 秀拓(絵)
【タイトル】こころを折らないで-父と娘の会話-【出版社】夢企画
【出版日】2012.06.03
-visual-selection-12.png)
#6 エッセンシャル思考
「書かれていることすべてが、今の俺と正反対のことばっかり……」
ビジネス書を読んでいると、大きく分けて2種類の感情が生まれます。
「へぇ! そういう考えもあるんだ~!」という新しい気づきと
「あぁわかるわかる。だよね~!」という共感です。
本によってだいたい4:6~6:4くらいに収まるのですが、本書はまったく違いました。
もうね、10:0。
新しい気づきしかない(笑)
加えて、いつ読んでもハッとさせられる。
「なんか最近、空回りしているなぁ」と思ったら必ず本書を読み、そしておおかた解決します。
エッセンシャル思考を一言で表すと、「本当に大切なことにのみ集中する」と一見シンプルですが、これがなかなか難しい。
本書に関しては、何か一つの起点を話すよりも、現在進行形の僕の現状を話した方が伝わると思います。
***
僕は2022年4月に会社員として新社会人生活をスタートし、2023年5月に会社員を辞めました。
同期の仲間は2ヶ月で終えた研修も、昔からマニュアルを覚えることが苦手な僕は半年でようやく修了。
そこから半年で辞めたわけですから、控えめに言ってスーパーお荷物社員です。
2023年5月からはアルバイトをしながら、自分でビジネスをスタート。
右も左もわからないながら師匠に教えを請い、収益も着々と伸びていきました。
この頃は「アルバイト」「自分のビジネス」「受注する仕事」が主な収入源であり、その割合は「2:4:4」と言ったところ。
正直、会社員時代より労働時間が圧倒的に多かったです。
俗に言う「一人ブラック企業」というやつですね、ハハ……(笑)
そんな激務に追われる日々を送ること1年。
ある日、トイレに絶妙なバランスで積まれたブックタワーを片付けていた時です。
タワーを構成するほとんどが漫画である中、ところどころにビジネス書が。
そこにあった一冊が本書『エッセンシャル思考』
たしか会社に勤め始めたくらいに買ったと思うのですが、当時の僕はあまりピンとこず、ちょっと読んで放置していました。
ただ、表紙が魅力的だったので、物は試しとページを開くと……。
もう、夢中になってイッキ読みしました。
当時の僕(と言っても半年前くらいですが)が、どれだけ「非エッセンシャル思考」だったのかを、嫌というほど思い知らされました。
僕は今まで「なんでも引き受け、それをこなすこと」が、仕事ができる人だと思っていました。
頼まれごとはすべて「YES」と答えることが、チャンスを掴む秘訣だと思っていました。
毎日疲れ果てて、倒れるように眠る毎日が「がんばっている証拠」だと思っていました。
ちなみに言っておくと、僕はこういう非効率的なアホみたいな努力をする時期も必要だと思っています。
ただ、いつかは非エッセンシャル思考からエッセンシャル思考に切り替える機会を設けないと、「自分が本当に望む人生は手に入らない」と、本書を読んで確信しました。
僕がなりたいのは「人々に勇気を届ける作家」
その目標に合わないことは、勇気をもって断る。
たとえ割の良い受注依頼や時給仕事でも。
そうでなければ、気づかぬうちに「ひとまずやらなければいけないこと」で日常が覆われ、目標が見えなくなってしまうから。
この価値観を持てたことは、僕の人生においてかなり大きな財産だと思っています。
***
「NO!」と断ることは、勇気がいることです。
すべてをこなさず、あえて「選ぶ」ことは、実はめんどくさいことです。
「本当に大切なこと」を見極めるのは、やみくもにがんばるよりも頭を使うことです。
でも、そこに「あなたが本当に望む人生」がある。必ずある。
あなたは本書『エッセンシャル思考』を読んで、どれだけのことを捨て、断り、見極めることができるでしょうか。
→ https://amzn.to/4gIyUHX
(マンガ版)
【著者】グレッグ・マキューン(著)、高橋 璃子(翻訳)
【タイトル】エッセンシャル思考【出版社】かんき出版
【出版日】2014.11.17
-visual-selection-7.png)
#7 藤原和博の必ず食える1%になる方法
「俺、ずっと勘違いしてたわ。
人生は足し算じゃなくて、かけ算勝負なんだ!」
「成り上がりたいビジネスパーソン必読の一冊」と、僕が勝手に言っている名著。
人生は「足し算勝負」ではなく「かけ算勝負」と気づいたところから、第二の人生が始まると思っています。
ちょっと耳が痛いところもあると思いますが、どうぞよしなに~。
***
たしか本書と出会ったのは、大学3年生の10月頃。
大学時代はソフトボール部に所属しており、この時期になると秋季大会が始まります。
当時はコロナ真っ只中で、開催が危ぶまれつつもなんとか開催。
西日本~全国大会を目指し、各自、猛自己練習の果てに臨んだ大会でした。
結果は惜しくも西日本大会に届かず、「5月の春季大会に向けてもう一度がんばろう!」とチーム一丸となって結束。
4年生の先輩たちはこの大会で引退だったため、少しの涙とともに「俺もあと一年か」と、ふと思いました。
そんな時に出会ったのが本書『藤原和博の必ず食える1%になる方法』です。
本書のメッセージを二文で表すと「1つの分野に1万時間を投下すれば、100人に一人の存在になれる」「3つの分野に1万時間を投下し、100万人に一人の人材になれ」です。
書籍の対象読者層としては、社会人以降のビジネスパーソンに向けられている内容ですが、当時大学生の僕にも刺さるものがありました。
僕は小学4年生(3年生だっけか?)から野球を始め、高校3年まで9年間。
そして大学のソフトボール3年間を合わせると、約12年もほぼ同じスポーツに時間を投下してきました。
1日5時間の練習を年200回続けたとして、10年で1万時間。
野球(ソフトボール)に関しては、100%余裕で超えてます。
もちろん、練習の「質」や「環境」で多少の差はつくかもしれませんが、練習時間で言えばどこの学校もおおむね同じ。
その中で将来プロ野球選手や社会人ソフトボール選手になり、「選手」として食っていける人が、ほんの一握り出てくるわけです。
僕も小さい頃からプロ野球選手を夢見ていましたし、ソフトボールに関しても真剣にやっていました。
でもやはり、「才能」の違いはあるものです。
同じ年齢、同じ時間、同じ練習をしても、僕より遥かに上手い選手がゴロゴロいる。
高校野球3年間。
僕はキャプテンにも関わらずほぼ毎日消灯係になるくらい、誰よりも練習していました。
誰よりもノックを受けたし、
誰よりもバットを振ったし、
誰よりも道具の手入れを欠かさなかった。
そう胸を張って言える自負があります。
「ホームランを打ちたい!」と毎日血豆を潰しながらバットを振っていたのにも関わらず、高校3年間一度も打つことはできなかった……。
でも、全体練習が終わるとすぐに友だちと遊びに行くチームメイトは、バカスカとホームランを打つ。
僕が見てないところで努力をしていた可能性も十分ありますが、それを考慮しても僕のメンタルはズタズタになり、端的に言うと「屈辱」でした。
その屈辱を、大学のソフトボールでも思い出してしまったんですよね。
秋季大会で僕らに勝った大学を、いとも簡単に叩きのめす、さらに強い大学。
その大学も全国大会に出たら、見るも無残にボロボロの大敗。
言い訳みたいであまり好きな言葉ではないですが、「上には上がいる」という現実を痛いくらいに感じました。
秋季大会が終わり、ひと時のオフ期間に出会った本書。
すぐに読み終え、僕はあと一年と少しの大学生活について考えました。
勉強、スポーツ、音楽。
記憶力、集中力、理解力。
継続力、逆算力、自己管理能力。
1の努力で1かそれ以上の結果をたたき出す力。
こういうのには「才能」がある。
負け惜しみみたいであまり言いたくないけど、僕の中では確信しています。
「1つのことを突き詰めて結果を出す『秀才』はいるけど、少なくとも野球(ソフトボール)に関しては僕じゃない」
「このまま2万時間、3万時間をかけても、おそらく僕は突出した人間にはなれない」
「だったらソフトボール(野球)はここで区切りをつけて、違う分野に新たな1万時間を投下しよう」
***
本書で得た「気づき」がこれまでの「体験」と結ぶつき、僕は3年の秋季大会を最後にソフトボール部を辞めることにしました。
その後は「次の1万時間投下先」を探すためにいろいろ体験することになるのですが、長くなるのでここまで。
この一連の出来事は24歳になった今でも、物事の「選択の根底」にある気がします。
懸命に努力してきた分野で「自分は突出できる才能はない」と自覚するのは、すごく苦しいことです。
努力量が大きければ大きいほどーそれこそ1万時間なんて軽く超える努力をしてきたことほどー「やめる」という決断は勇気がいることでしょう。
でも、もしかしたら「次の1万時間投下先」が、あなたの才能を開花させる場所かもしれません。
それでなくとも、また次、その次、と1万時間投下先を増やすにつれて、あなたは100万人に一人の存在になっていきます。
本記事では「本書を読んで僕が感じたこと」をメインでお話していますが、実際の内容としては人々を4タイプに分類して、それに見合った1%の人になる方法を詳しく教えてくれています。
誇張せずに言って、本当に面白いです。
「今いる場所で懸命にがんばっているけど、なかなか結果(出世、記録、収入 など)に結びつかない……」という人。
そして「努力量と現実の乖離に苦しむ人」にも、おすすめの一冊です。
【著者】藤原 和博
【タイトル】藤原和博の必ず食える1%の人になる方法【出版社】東洋経済新報社
【出版日】2013.08.22
-visual-selection-8.png)
#8 なまえのないねこ
「最後の最後でハッと気づかされる傑作。僕が絵本を好きになったキッカケです」
言わずも知れた名作絵本。
心温まるイラストに、「ハッ」と大切なことを気づかされる一冊。
全32ページを読み終え、僕は「ちゃんと人の名前を呼ぼう」と決めました。
***
本書の紹介はビジネス書と比べてページ数も少ないので、内容にはほぼ触れません。
ただその代りに「承認欲求」について、少し考えてみてほしいです。
承認欲求とは、「周囲から認められ、自分の価値を感じたい!」という心理のことです。
人間は「群れ」の生き物である以上、必ず承認欲求を持っています。
山にこもって悟りを啓く以外、ゼロにすることはできないでしょう。
承認欲求を「適度に」持つことは、良いことです。
たとえば部活動なら、監督に認めてもらいスタメンになるため。
会社なら、上司に認めてもらい出世するため。
承認欲求があるからこそできる努力もあると思います。
ただ、承認欲求が「強すぎる」とかえって悪影響も……。
昨今でいうと、SNSの「いいね」を過剰に欲する若者がわかりやすいでしょう。
「いいね」欲しさに公序良俗に反する投稿をしてしまう問題も増えています。
他にも、承認欲求が強すぎると「自分が認められないのに、なんであの人だけ……!」と、他人の活躍に嫉妬を抱きやすくなります。
その結果、他人を下げて自分を優位に立たせる言動に繋がりかねません。
SNSやメディアでは「アンチ」と表現されることも多いですね。
「承認される機会が少ない人ほど、承認欲求が強い」
このジレンマは、どれだけ考えても仕方がないことです。
僕も若干……いや、かなり承認欲求が強い方でしたからね。
特に中学校~高校~大学と、「部活動」をやっていた期間は承認欲求の権化みたいな性格だったと思います。
さて、ここからどんどん路線がズレていきそうなので話を戻して。
僕は本書を読んで、「人を名前で呼ぼう」と決めました。
この絵本を読んだのは、部活動を引退して就活も終えた大学4年生の頃。
当時は仲良い友だちを「お前」と読んだり、大学の教授も「先生」とひとくくりに呼んでいました。
でも、みんなそれぞれ、名前があるんですよね。
両親につけてもらった、大切な名前が必ずあるんですよね。
だったらしっかり名前を呼ぼう。
友だちは名前で、教授は「○○先生」と。
たぶんそれが、ほんの少しだけでも承認欲求を満たすことに繋がるから。
人は「おい!」とか「お前!」とか「バイト!」とか「新人!」とか。
名前で呼ばれない環境では、どうも承認欲求を得るのが難しいように感じます。
「しょうたくん」
「しょうたさん」
「片山くん」
「片山さん」
名前で呼んでくれる環境というのは、少なからず「居場所」になりますし、僕がそうなれるように「名前を呼ぼう」と決めました。
今回感じた例は、あくまでも僕の過去や体験があっての話です。
子どもはもちろん、大人でも人によって感じ方が変わると思うので、ぜひ一度読んでみるといろんな気づきを得られると思います。
【著者】竹下文子(著)、町田尚子(イラスト)
【タイトル】なまえのないねこ【出版社】東洋経済新報社
【出版日】2013.08.22
-visual-selection-9.png)
#9 自分の中に毒を持て
「自分の成功は、自分で決められる」
火花が散るようなアツイ一冊。
人生の岐路に立っている人、人生に悩んでいる人にはぜひ読んでいただきたい。
僕も時折り、弱い自分が顔を出してきたときは、必ず本書を読み返しています。
***
本書の著者・岡本太郎氏は日本を代表する芸術家・画家・彫刻家。
大阪にある『太陽の塔』は、すごく有名ですよね。
「芸術は爆発だ!」の名言もそう。どこかで聞いたことあるのではないでしょうか。
彼は前衛芸術の旗手として活躍し、独創的でエネルギッシュな作品を数多く生み出しました。
(※前衛芸術:伝統的な芸術の枠にとらわれず、新しい表現や手法に挑戦する芸術のこと)
太郎氏は、その破天荒で独創的な性格や言動から、世間や美術界の一部から批判を受けることが多かったそうです。
僕はあくまで本書に刺激を受けたのであって、作品の大ファンというわけではありません。
それでも彼の作品を見ると、独特のエネルギーやインパクトを感じ、一目で「岡本太郎の作品だ!」とわかる特徴を感じました。
『太陽の塔』『明日の神話』『歓喜』とググってみてください。
一見すると「なんだこれ!?」と驚かされる作風でありながらも、何か不思議なパワーが伝わってくると思います。
そんな太郎氏の「常識を疑え!」「芸術は爆発だ!」という主張。そして世間に迎合しない生き方が、「大きなことを成し遂げよう!」と目標を掲げる人に強烈な刺激を与えてくれるはずです。
僕も「これやりたいけど……できるかな?」「周りにどう思われるかな?」という言葉が心に浮かぶときは、毎度強烈な刺激を与えてもらっています。
【著者】岡本太郎
【タイトル】自分の中に毒を持て【出版社】青春出版社
【出版日】2018.02.15
-visual-selection-10.png)
#10 嫌われる勇気・幸せになる勇気
「結局、この本に帰結する」
ラスト10冊目。やっぱり最後はこの本を語りたかった。
王道中の王道、『嫌われる勇気』『幸せになる勇気』です。
ちなみに『嫌われる勇気』『幸せになる勇気』はそれぞれ別の本なので、厳密には二冊ですが、そこはちょっと多めにみてくださいな。
今回ご紹介した10選の中でも、最初に紹介した『上京物語』と同じくらい、何度も読み返している書籍です。
***
まず、本書はオーストラリアの精神科医を務めたアルフレッド・アドラー氏が提唱した『アドラー心理学』を基に、物語が構成されています。
そのアドラー心理学を知る哲人。
そして、過去に失敗やコンプレックスを持つ青年。
本書『嫌われる勇気』『幸せになる勇気』はこの2人の会話によって構成されており、「著者が一方的に語る」という一般的なビジネス書・自己啓発書ではありません。
なので、純粋に「読み物」としてもかなり面白い本です。
嫌われる勇気・幸せになる勇気(アドラー心理学)では、一貫して「幸せ」と「勇気」について語られています。
幸せになるための勇気を持つために。
目からうろこの様々な考え方が、書籍を通じて知ることができます。
- 課題の分離
- 目的論
- 劣等コンプレックス
- 優越コンプレックス
- 承認欲求
- 人間関係
- 人生の課題
あぁもう……話したいことがありすぎて、このまま一冊の本が書けちゃいそうです(笑)
一見すると、言葉が難しく感じるかもしれませんが、それを会話形式でわかりやすく解説してくれるのが本書の魅力。
「本」というか、どちらかというと「脚本」みたいなイメージが近いかもしれません。
セリフがメインで読書があまり得意でない人でも、楽しく読めると思います。
***
僕がこの二冊を読んで1番実生活に活かせた〝気づき〟をご紹介します。
(たくさんありますが、ネタバレになってしまうため)
それが「これからどうするか?」という未来を描く思考です。
僕たち人間は得てして、「過去の自分」に思いを巡らせてしまいます。
「あのとき、あんなこと言わなければ……」
「わたしはなんてことをしてしまったんだ…….」
「取り返しのつかない失敗をしてしまった……。もう人生に希望が持てない」
何か起こると「過去の自分」に対し、怒り、嘆き、失望の感情を抱くことでしょう。
いや、もっとストレートに言うのなら「過去の自分に思いを巡らせることで、〝今の自分を変えること〟から逃げる」選択をしているのです。
自分の心に正直になると、思い当たる節はけっこうありませんか?
でも、この地球には「今」しかありません。
未来も「今」の延長線上にあるだけ。
誰が何と言おうと、過去にどんな大失敗をしようと。
考えるべきことは「今、この瞬間からどうするか?」しかありません。
なるべく断定的な口調を避ける僕も、ここだけは断言します。
過去に言い訳せず、未来に過信せず。
ただただ愚直に「今」を生きる。
僕はこの思考がベースになったからこそ、自分の心に正直に生きられるようになったと思っています。
しかしながら、こんな偉そうに語っている僕も、まだまだ未熟者です。
意味がないとわかっていながらも、ついつい過去に失望し、未来に不安を覚えてしまうこともあります。
僕自身も、今この記事をお読みくださっているあなたとともに、精進していきたいと思います。
少し話がそれましたが、ぜひこの2冊を読んで、あなたも「今ここ」を生きる勇気をみにつけてみてください。
→ 嫌われる勇気
【著者】岸見 一郎、古賀 史健
【タイトル】嫌われる勇気【出版社】ダイヤモンド社
【出版日】2016.02.26
→ 幸せになる勇気
【著者】岸見 一郎、古賀 史健
【タイトル】幸せになる勇気【出版社】ダイヤモンド社
【出版日】2016.02.26
-visual-selection-11.png)
まとめ
#1 上京物語
#2 チーズはどこへ消えた?
#3 夢をかなえるゾウ(シリーズ)
#4 死ぬ瞬間の5つの後悔
#5 こころを折らないで-父の娘の会話-
#6 エッセンシャル思考
#7 藤原和博の必ず食える1%になる方法
#8 なまえのないねこ
#9 自分の中に毒を持て
#10 嫌われる勇気・幸せになる勇気
約13600文字と、軽い電子書籍くらいのボリュームになりましたが、いかがでしたか?
本記事では、『社会人こそ読書が必要な理由と必読10冊』について、僕自身のエピソードとともにご紹介してきました。
読書は単なる知識の蓄積ではなく、〝気づき〟を得ること。
そこから〝価値観〟が徐々に変わり、
人生をより良くするための〝選択〟ができるようになる。
そうすることで日々の〝習慣〟が変わり、
ひいては〝現状〟にも変化が起こる。
少なくとも、僕はそう確信しています。
価値観が選択を生み、選択が習慣を形成し、習慣が現状を創る。
そのためには、視野を広げること、つまり手段の一つである「本を読むこと」が大切なのです。
本記事でご紹介した10冊は、そのどれにも大切な気づきがあり、「今をどう生きるか?」を考えさせられます。
今回ご紹介した〝気づき〟は、あくまで僕の主観なので、人ぞれぞれ、いろんな受け取り方があると思います。
ぜひ、読んでみてくださいね。
それでは、最後までお読みいただきありがとうございました!
ちなみに、『新社会人&社会人に備える大学4年生に特化したおすすめ書籍12冊』は下記の記事で解説しております!
読書が苦手な方でも、毎月1冊読めるように。
僕が「新卒・大学4年生でこの本を読んでおいてよかった! 読んでおきたかった!」と心から思う書籍を12冊紹介しています。
ぜひ2025年は、毎月1冊でもいいから本を読んでみてくださいね。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
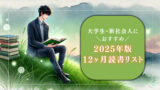

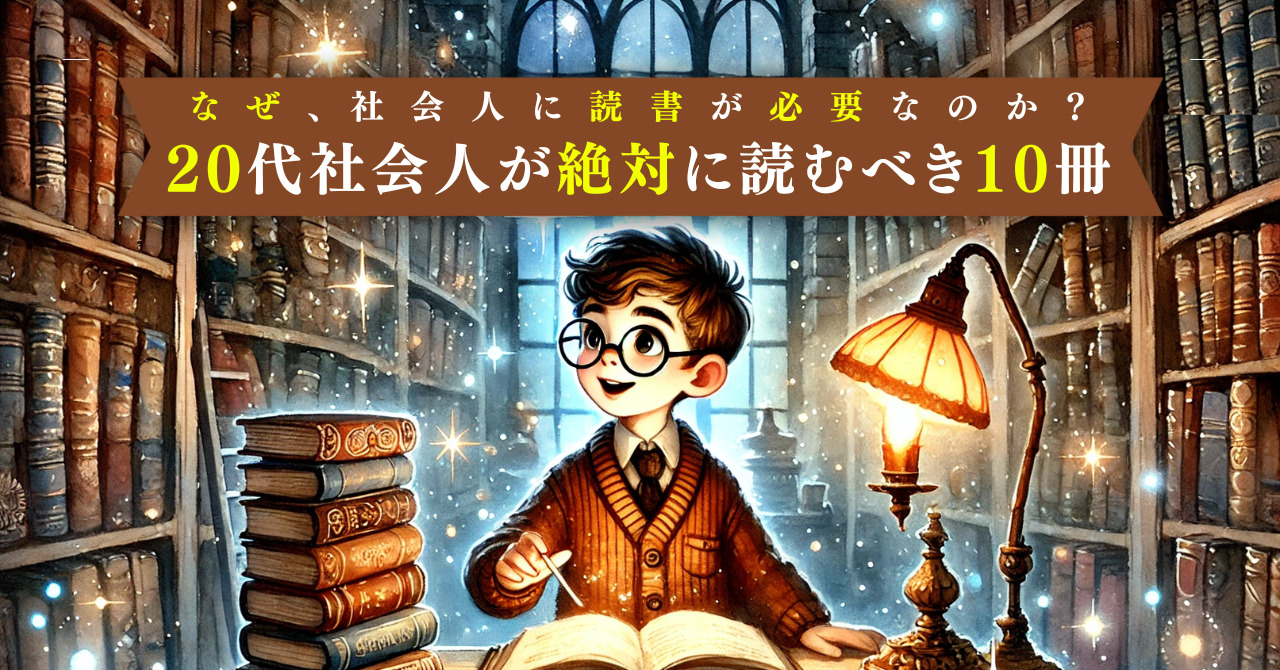

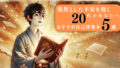
コメント